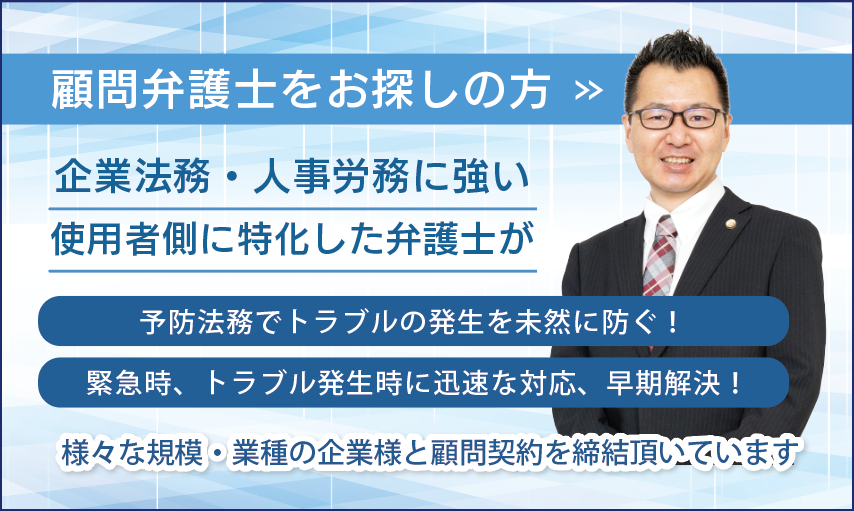目次
1.メンタルヘルス問題について会社が知っておくべきこと
1-1.従業員のメンタルヘルス問題と会社の責任
近年、従業員がうつ病等の精神疾患を発症し、自殺に至るケースを耳にする機会が増えてきました。
精神疾患を発症する原因はさまざまですが、過重労働やハラスメントなどが原因の場合、会社は安全配慮義務違反(労働契約法5条)による責任を問われる可能性があります。
そこで、本記事では、従業員のメンタルヘルスに関する労災認定の方法、会社がすべき対応等についてご説明します。
1-2.労働基準監督署の労災認定
ア 業務起因性の判断枠組み
うつ病などの精神障害についても、労災認定されるためには業務起因性が認められなければならないところ、精神疾患の発症やそれに引き続く自殺が労災認定されるかどうか(業務起因性が認められるかどうか)は、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平23・12・26基発1226第1号。以下、「23年認定基準」といいます。)に基づき判断されます。
23年認定基準は、精神の破綻は環境由来のストレスと個体側の反応性、脆弱性との関係で生じるとされ、ストレスが強ければ個体側の脆弱性が小さくても精神障害を発症するし、個体側の脆弱性が大きければストレスが小さくても精神障害を発症するという「ストレス―脆弱性理論」に基づいて、次の①~③を労災認定の要件としています。
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
①の「認定基準の対象となる精神障害」とは、統合失調症、うつ病、強迫性障害、適応障害などが主たるものです。
②にいう「業務による強い心理的負荷」に該当するかどうかは、心理的負荷の強度を強・中・弱の3段階に分類した「心理的負荷評価表」(別表1)において、総合評価で「強」と判断された場合に、「業務による強い心理的負荷」に該当すると考えられています。
③のうち「業務以外の心理的負荷」については、心理的負荷を与える具体的出来事とその負荷の強度を例示した「業務以外の心理的負荷評価表」(別表2)が定められており、強(「Ⅲ」)と判断される業務以外の心理的負荷がある場合には、発病の原因が業務による強い負荷(②)にあるのか、業務以外の強い負荷にあるのかを医学的観点から判断するとされています。
「個体側要因」については、精神障害の既往症やアルコール依存などの要因がないかどうか等が例示されています。
なお、「ストレス―脆弱性理論」に基づいていることから、業務起因性を判断する際には、どのような人を基準に判断すべきかが問題になるところ、23年認定基準では「同種の労働者」(職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者)を基準とするとされています。
イ 労働者の自殺と業務起因性判断
労働者の自殺は、労働者の「故意」による死亡として労災保険給付が支給されないことがあります(労災保険法12条の2の2第1項)。
しかし、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(平11・9・14基発544号、平成21・4・6基発0406001号)において、業務による心理的負荷によって精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、または自殺を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたものと推定し、原則として業務起因性が認められるとされました。
裁判例でも、業務に起因して精神障害を発病したと認められ、労働者が自殺した場合には、(業務と精神障害との間だけでなく)精神障害と自殺(死亡)についても業務起因性を肯定するものが多く存在します。
以上が23年認定基準の概要ですが、詳細は厚生労働省のパンフレットにわかりやすく記載されていますので、こちらもご参照ください(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf)
1-3.裁判所の労災認定
労働基準監督署の労災認定を受けたとしても、労災保険給付には上限が設けられているため、それだけでは損害のすべてを回復できない場合があります。
その場合、被災労働者・その遺族から、使用者に対して損害賠償を求める民事訴訟を提起されることがあり、使用者が安全配慮義務(健康配慮義務)に違反し、労働者が精神疾患・自殺に至った場合には、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになります。
上記のような民事訴訟においても、上記(2)に記載した「ストレス―脆弱性理論」、23年認定基準を参考に、使用者の責任や損害賠償額が判断されることになります。
ただし、心理的負荷の基準となる平均的労働者をどのように考えるか、相当因果関係、予見可能性、素因減額、過失相殺などについて裁判所の判断が分かれることがあります。以下では、これらの点についてご説明します。
ア 平均的労働者
裁判例においても、上記(2)のとおり、「強い心理的負荷」が認められるかどうかは、職種、職場における立場や職責、年齢、経験が類似する「同種の労働者」が一般的にどう受け止めるかを基準に判断するものが多いです。
もっとも、「同種労働者(職種、職場における地位や年齢、経験等が類似する者で、業務軽減措置を受けることなく日常業務を遂行できる健康状態にある者)の中でその性格傾向が最も脆弱である者(ただし、同種労働者の性格傾向の多様として通常想定される範囲内の者)」を基準とした名古屋地判平成13年6月18日をはじめとし、少し幅のある判断をしているように見受けられるものもあります。
イ 相当因果関係
使用者の損害賠償責任が肯定されるためには、社会通念上、業務に内在し又は通常随伴する危険が現実化して精神疾患を発症したと法的に評価できること、つまり相当因果関係が認められることが必要になります。
本来は、労災認定における業務起因性の判断と民事訴訟における安全配慮義務違反・相当因果関係の判断は別の問題といえますが、多くの裁判例では、業務起因性の判断と民事訴訟における安全配慮義務違反・相当因果関係の判断は重なる傾向があると思われます(ただし、前橋地判高崎支判平成28年5月19日など、労災保険法上の業務起因性の判断と民事訴訟における安全配慮義務違反の判断が分かれたものもあります)。
ウ 予見可能性
使用者は、事故や疾病等の結果の発生について予見可能性がなかったことを立証できれば、安全配慮義務違反による責任が否定されます。
この「結果の発生」に対する予見可能性について、精神疾患を発症しその後自殺したという事案の場合は、「精神疾患を発症する」予見可能性と、「自殺」の予見可能性の二段階の予見可能性が認められるかが問題となります。
まず、「精神疾患を発症する」予見可能性については、長時間労働により精神疾患を発症した事案の多くの裁判例は、労働者の健康状態の悪化を認識していなくとも、就労環境等に照らして、労働者の健康状態が悪化する恐れがあることを容易に認識し得た場合には、「精神疾患の発症」についての予見可能性を認める傾向にあります。
さらに、「自殺」の予見可能性について、長時間労働の継続などにより疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると労働者の心身の健康を損なうおそれがあることは広く知られているところであり、うつ病の発症及びこれによる自殺はその一態様である」として、使用者が業務の過重性を認識する限り、自殺についても予見可能性を肯定する裁判例があります。
以上の裁判例から、使用者の「労働者が精神疾患にり患していることに気付かず、自殺するとは思っていなかった」という主張は認められない可能性があります。
エ 素因減額・過失相殺
使用者の安全配慮義務(健康配慮義務)違反が認められる場合でも、労働者の姿勢・態度、基礎疾患などの事情が損害の発生・拡大に寄与しているときは、使用者の損害賠償額の調整が行われることがあります。
もっとも、以下の判例のように、性格や体質を理由とする訴因減額(過失相殺)は容易には認められない傾向にあります。
判例(最判平成12年3月24日)では、「労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り」、過失相殺の対象として斟酌することはできないとしています。
また、労働者が自らの病気に関する情報を使用者に申告していないことをもって、使用者の安全配慮義務違反に基づく損害賠償の額を定めるにあたって過失相殺をすることはできないとした判例(最判平成26年3月24日)もあります。
2.会社がすべき対応
2-1.労働時間の状況把握
精神疾患を発症してしまう代表的な原因は長時間労働です。裁判例においても使用者が労働時間管理を適切に行っていたかが問われることが多いといえます。
そこで、会社としては、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月6日基発339号)、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日基発0120第3)を参考にして、適切な労働時間管理をする必要があります。
なお、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者については、会社が労働時間把握する義務はありませんでしたが、平成30年法改正により、高度プロフェッショナル制度(高プロ制度)対象者を除き、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者についても労働時間の状況を把握する義務が定められました(労働安全衛生法66条の8の3)。
2-2.いじめ・嫌がらせ(ハラスメント)の防止
いじめ、嫌がらせも精神疾患の原因となることが多いため、会社としては、いじめ・嫌がらせ(ハラスメント)の防止措置を講じておくことが重要になってきます。
具体的には、労働者のセルフチェックを定期的に実施する、労働者が気軽にメンタルヘルス・ハラスメントに関して相談できる窓口を設置する、ハラスメントに関する研修を実施するなどが考えられます。
なお、法改正により、1年以内ごとに1回の定期的なストレスチェック及びその結果に基づく面接指導の実施義務が課せられました(労働安全衛生法66条の10)。
ただし、労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務とされていますが、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策としては有用だと思われます。
2-3.長時間労働者への面談指導の実施
平成30年法改正により、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対して、使用者は、当該労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければならないと定められました(労働安全衛生法66条の8、同法規則52条の2第1項)。
2-4.研究開発事務従事者、高度プロフェッショナル制度の対象労働者への医師による面談指導の実施
上記の者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間を超える場合には、労働者からの申出にかかわらず、医師による面接指導を実施しなければなりません。
2-5.病状等の確認、配転、業務軽減措置
労働者が不調を訴えた場合、本人との面談、主治医との面談、産業医等の受診などを行い、病状等を確認しておく必要があるでしょう。
なお、病状等を確認する方法として、受診命令を発令するのも方法の一つですが、精神疾患に関する受診命令の有効性については、プライバシー侵害のおそれが大きいとして否定的な見解を示す裁判例(名古屋地判平成18年1月18日)も存在することに注意が必要です。
その上で、安全配慮義務の履行として、配転、業務軽減措置等を行う必要が生じる場合があります。
3.メンタルヘルス問題に関して千瑞穂法律事務所ができること

4.メンタルヘルスに関するご対応の弁護士費用
初回ご相談は無料です。その他弁護士費用についてはこちらをご覧ください。
5.ご相談の流れ
千瑞穂法律事務所に企業法務にまつわるご相談や各種お困りごと、顧問契約に関するご相談をいただく場合の方法をご説明します。

【1】 お電話の場合
「082-962-0286」までお電話ください。(受付時間:平日9:00〜17:00)
担当者が弁護士との予定を調整のうえ、ご相談日の予約をおとりします。
【2】 メールの場合
「お問い合わせフォーム」に必要事項をご入力のうえ、送信してください。(受付時間:年中無休)
送信いただいた後に担当者からご連絡し、ご相談日の予約をおとりします。

(ご相談時刻:平日9:30〜19:00)
※ 夜間や土日のご相談をご希望のお客様については、できるかぎり調整しますのでお申し出ください。

見積書をご確認いただき、ご了解いただいた場合には、委任状や委任契約書の取り交わしを行うことになります。

この場合、当該案件について電話やメールによるご相談が可能です。
進捗についても、適時ご報告いたします(訴訟対応の場合、期日経過報告書をお送りするなどのご報告をいたします)。