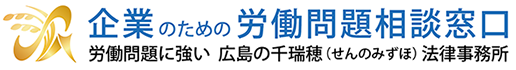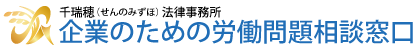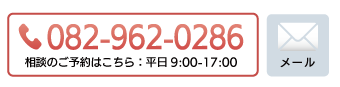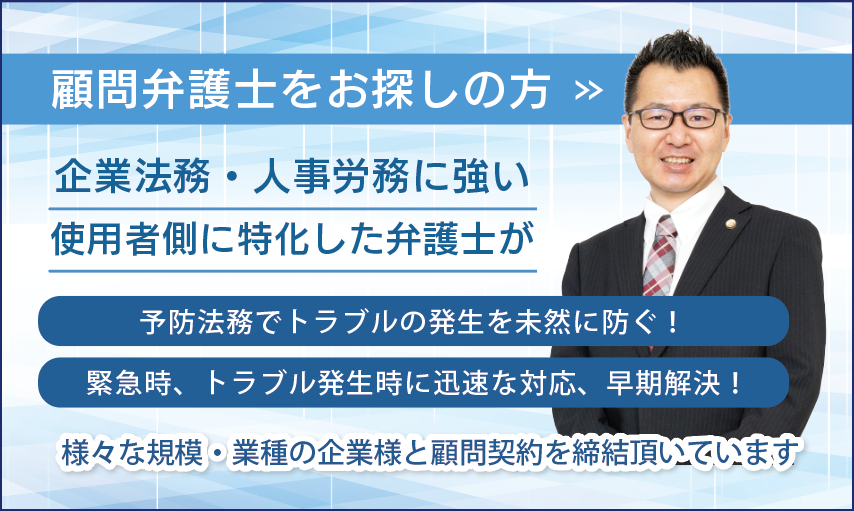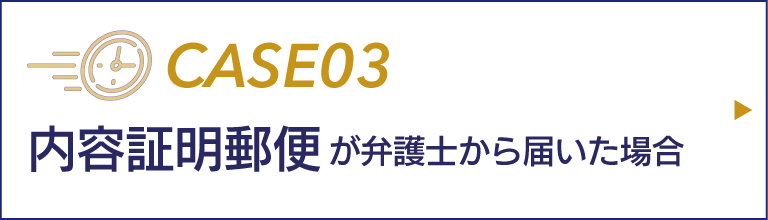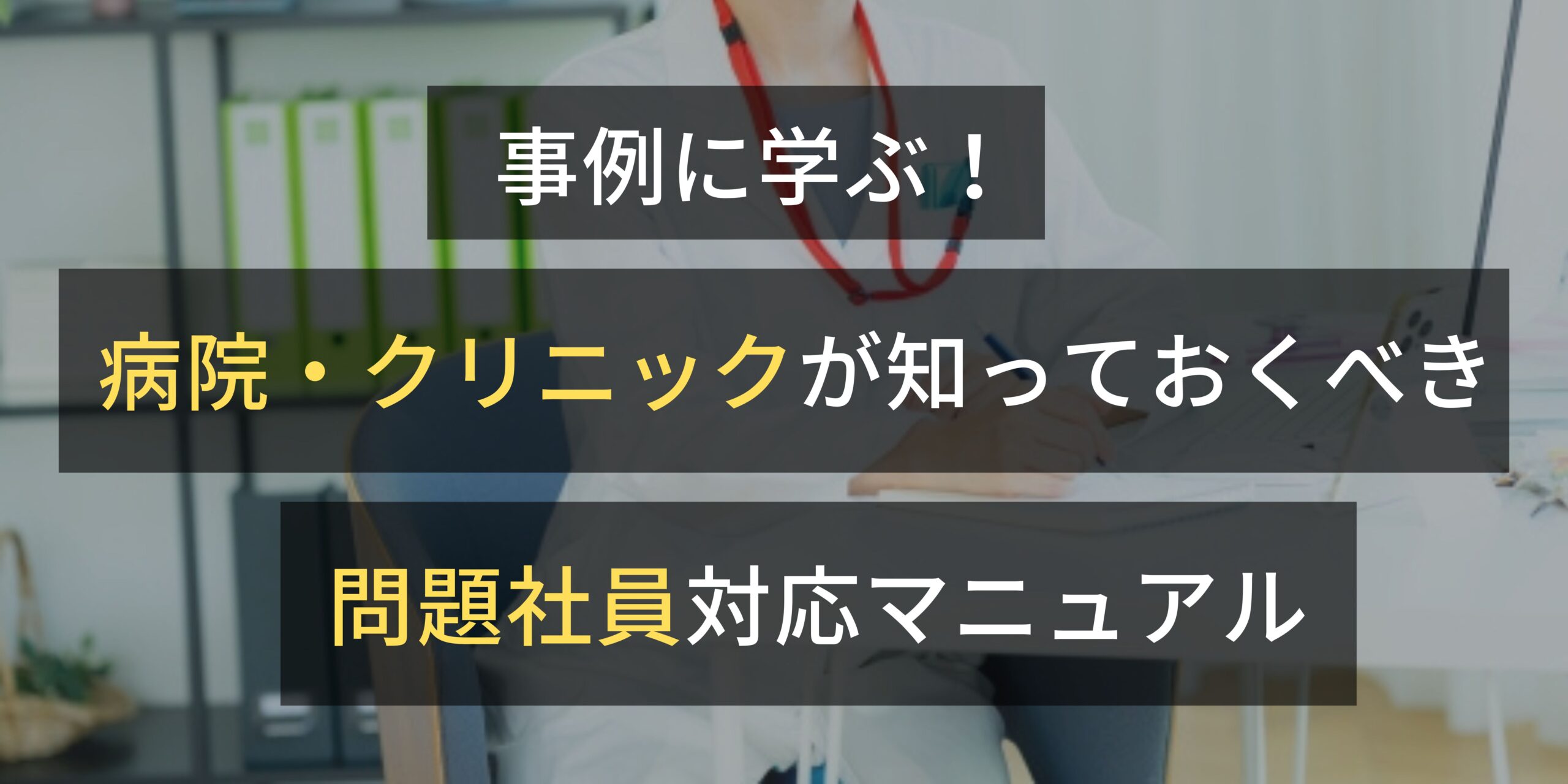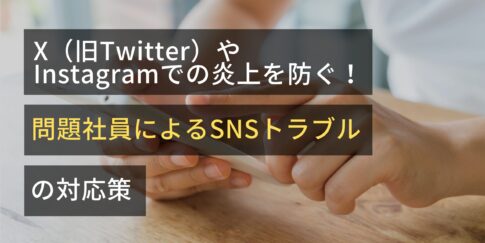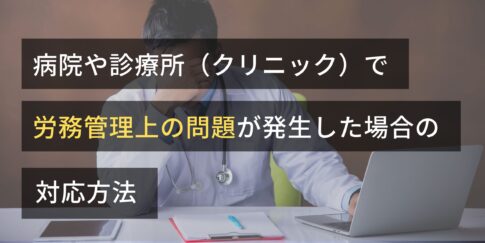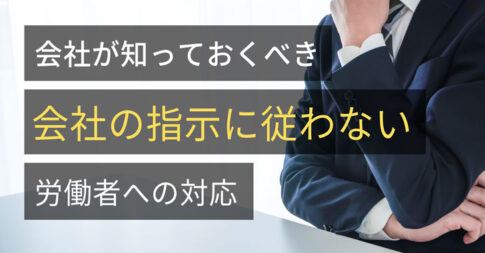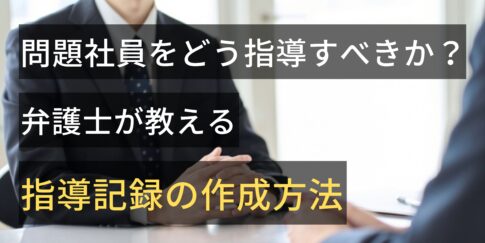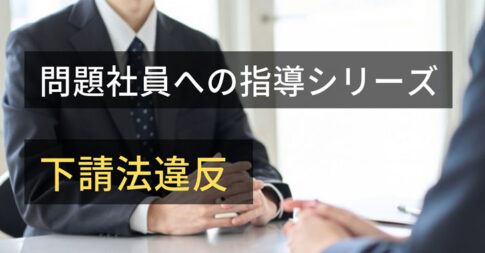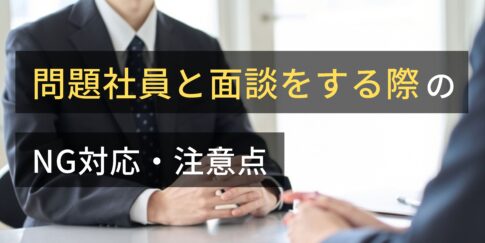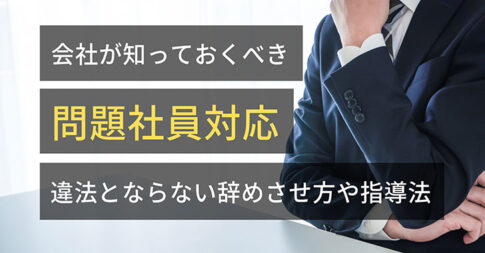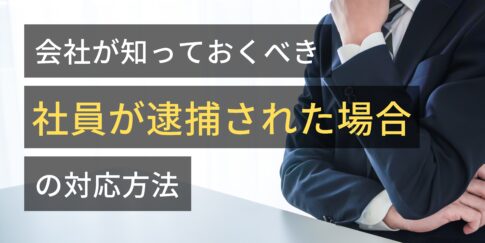企業において上司の指示に従わない、協調性がないなどの社員は問題社員と呼ばれ、企業に対して様々な悪影響を生じさせてしまいます。そして、そのような問題は病院・クリニックなどの医療機関でも生じうることです。
医療現場においては患者とスタッフの間のみならず、スタッフ間の円滑なコミュニケーションが重要なことは言うまでもないことと思われます。医療機関において問題社員を放置することは、スタッフ間の円滑なコミュニケーションを阻害し、結果として優秀なスタッフを失ってしまうことにもつながりかねません。そのため、問題社員に対して何らかの対応を行うことは必要不可欠です。
一方で問題社員に対して適切な対応をしなければ、退職時にもめたり、最悪の場合、問題社員から訴えられ、損害賠償請求をされたりするなどのリスクがあります。そして、病気の進行度合いに応じて医師の取るべき対応が変わるように、問題社員にどのような対応をするべきかについてもスタッフによる問題行動の開始時期や種類などの状況に応じて異なります。
そこで、本記事では、病院・クリニックの院長や人事担当者様が知っておくべき一般的な問題社員対応マニュアルをご説明いたします。
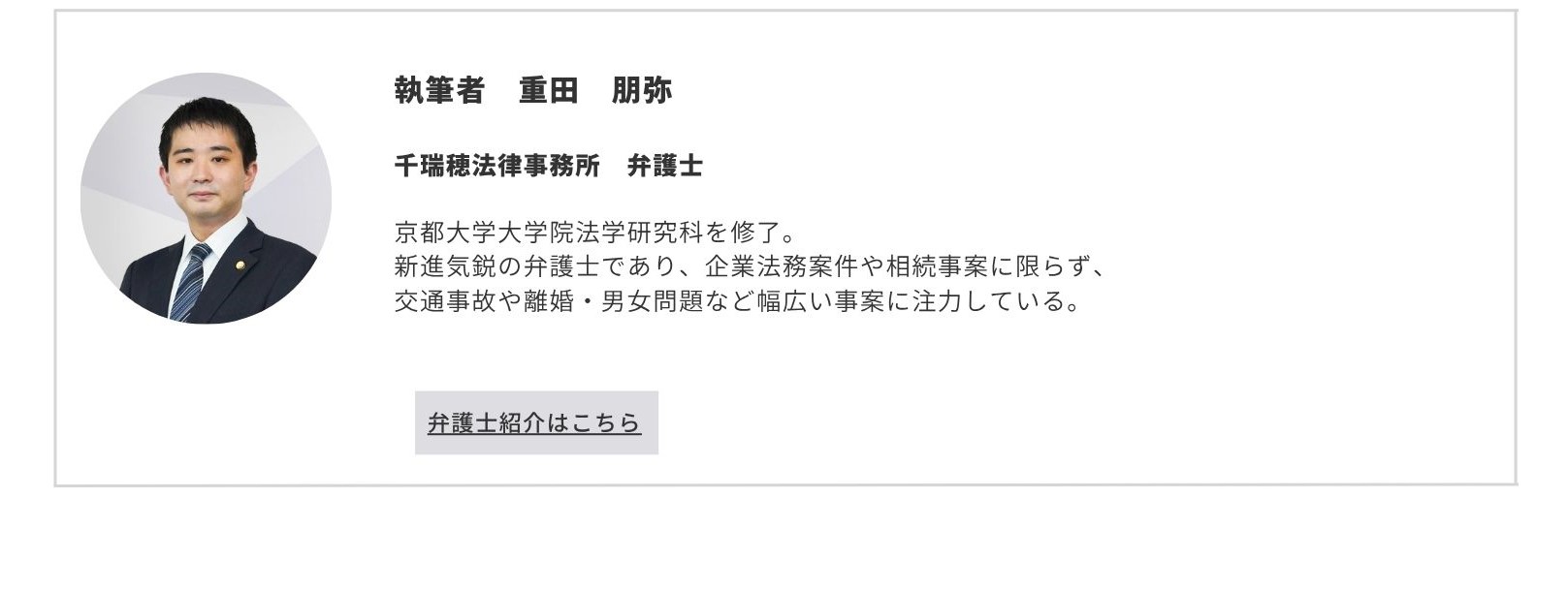
目次
1.病院・クリニックの問題社員とは
問題社員とは、一般的に、与えられた仕事をしない、遅刻、無断欠勤をくりかえす、上司の指示に従わないといった、職場において問題行動をする社員を言います。
問題社員に対して何らかの対応をしなければ、問題社員と直接かかわる人に迷惑が生じるだけでなく、職場全体の士気が下がってしまい、結果として優秀なスタッフが働きにくい環境となってしまいます。
病院・クリニックのような医療機関においても上記のような行動をする問題社員は存在し得ます。また、特に医療機関においては、他のスタッフに対して強く当たり職場の雰囲気を悪くする、患者の診療を拒絶するといった行動をとるスタッフも問題社員となるでしょう。医療機関では、他の業種と比べてもスタッフ同士のコミュニケーションが重要であり、これらの事態に適切に対応する必要性が非常に高いといえます。
2.問題社員を懲戒・解雇するリスク
このような問題社員に対する対応として、まず懲戒や解雇が思い浮かぶでしょう。もっとも医療機関とスタッフの間にも雇用契約が締結されている以上、労働契約法の適用があります。そのため、「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」といえる場合でなければ、懲戒・解雇は無効となります(労働契約法15条、16条)。この「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当」はそのような対応をするほど重大な理由や適切な手続きを踏む必要があり、安易に懲戒や解雇をしても無効となる可能性が高いです。
そして、無効となるような解雇をした場合、問題社員によって損害賠償請求をされてしまう恐れがあります。このような請求がなされた場合、一般的には、当該社員の年収を基準として給与の数カ月から数年分ほどの金銭を賠償金ないし解決金として支払うこととなります。更によくあるケースとして、問題社員が職場の他の社員を巻き込んで、複数のスタッフが損害賠償請求をするケースがあり、そうなった場合、医療機関に生じる損害は数千万円となる可能性もあるでしょう。
このように、問題社員を安易に懲戒・解雇すると、後に解雇が無効であるとして多額の賠償金を支払うリスクがあることに注意するべきです。
3.病院・クリニックの問題社員に対するステージ別対応マニュアル
2で説明した通り、問題社員がいると判明したからといって安易に懲戒・解雇を行うのはリスクがあります。そこで、以下では、問題社員の状況別に病院・クリニックが行うべき対応マニュアルをステージ0~Ⅳといった段階に分けて説明いたします。なお、法律上ステージ0~Ⅳといった用語はありませんが、問題社員の状況を示す用語として、便宜上使用させていただきます。
また、全てのステージに共通して必要なこととして、問題社員による問題行動が発覚した段階では、必ず、そのような事実が実際に存在するかの調査を行う必要があります。
(1) ステージ0~Ⅰ(初期)
ステージ0~Ⅰ(初期)とは、問題社員による行動が初期段階、すなわち、問題社員の問題行動が始まったばかりである場合や職場全体に生じている影響が小さい場合を指すこととします。
このような場合の対応としては、まず、問題社員に対して注意・指導を行うこととなります。この際の注意点として、病院・クリニックが問題社員に対して注意・指導を行ったことを病棟管理日誌等に記録したり、問題社員とのメール等のやりとりがある場合には保存したりするなど、後の処分等で争われた場合に備えて証拠を残しておくのが望ましいでしょう。
また、指導を口頭でする場合に、業務と関係のない人格否定のような言動をすると、問題社員から訴えられてしまう可能性もあるため、冷静に注意・指導をすることを心掛ける必要があります。
なお、ステージⅠ(初期)の段階では、注意・指導によって問題社員の行動が改善する可能性も十分あり、費用対効果の点からみても弁護士に依頼する必要性は低いです。
(2) ステージⅡ~Ⅲ(中期)
ステージⅡ~Ⅲ(中期)とは、問題社員による行動が中期段階、すなわち、上記問題社員の行動が注意・指導でも収まらない場合や問題社員の行動が医療機関に相当程度大きな悪影響を生じさせる場合を指すこととします。
このような場合の対応としては、減給や降格などの何らかの懲戒処分をすること、別の科へ配置転換をすること、場合によっては退職勧奨をすることも考えられます。これらの対応をする際にはそれぞれの対応に応じて注意点があります。
まず、減給や降格などの懲戒処分といった対応を行う場合には、就業規則に懲戒について定めていること、当該処分を行う「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要となります(労働契約法15条)。そのため、懲戒について就業規則に定めがあるか、問題社員の行動について証拠があるか、処分は重すぎないか、社員自身に弁明の機会を与えたかという点を検討したうえで上記対応をする必要があります。
次に、配置転換について、配置転換はスタッフの同意なく行うことができますが、業務上の必要性が存在しない場合、配置転換が不当な動機・目的をもってなされた場合、配置転換によって生じる不利益が通常甘受すべき程度を著しく超える場合には配置転換が無効となるとされており(最判昭和61年7月14日 東亜ペイント事件参照)一定の制限があります。そのため、病院・クリニックなどの医療機関がスタッフを配置転換する場合には、上記の判例を踏まえ、他の科に配属することによりスタッフに生じる不利益が大きすぎないかといった点に注意して対応するほか、スタッフの同意のもと配置転換する場合には同意書を書面で残すことを注意するべきでしょう。
なお、よくある事例として、雇用契約書等に「業務の内容を●●病院における看護業務」というように勤務地を限定していることがありますが、そのような場合には他の病院に配置転換ができないため注意しておく必要があります。
最後に退職勧奨についてですが、そもそも退職勧奨とはスタッフの合意のもと病院・クリニックを辞めてもらうものであり、退職勧奨を強要する場合には違法となります。そのため、退職勧奨という対応をする場合には、退職勧奨の面接の回数や時間を合理的な範囲とするほか、退職合意書を作成するなどの注意をする必要があります。
ステージⅡ~Ⅲ(中期)となった場合、懲戒処分や配置転換の有効性についてのリーガルコメントの提供を受けたり、退職勧奨における合意書の作成を依頼したりするなど、弁護士等の専門家を利用する必要性が高いといえます。
そして、早期に相談すれば、後に問題社員から訴えられたとしても、金銭の支払いを免れる又は少なくて済むという結果となることが多いため、この段階に入った場合にはできる限り早く弁護士等の専門家に相談する方がよいでしょう。
(3) ステージⅣ(末期)
ステージⅣ(末期)とは、問題社員による行動が末期段階、すなわち、問題社員が会社に与える影響が著しく大きくなった場合や問題社員から解雇無効の訴えをなされた場合を指すこととします。
このような場合の対応としては懲戒解雇が考えられます。また、この際、退職勧奨も同時に行うことも有りうるでしょう。かかる対応をする際には、3(2)の懲戒処分及び退職勧奨に記載した事項と同様のことを注意するべきです。
なお、この段階となると問題社員も紛争を見越して発言等を録音している可能性が高いことから、発言等は慎重に行うべきです。
ステージⅣ(末期)となった場合には紛争性も高く、弁護士等の専門家に依頼する必要性は高いです。もっとも、ステージⅣ(末期)となってから弁護士等に相談する場合、問題社員との紛争解決は厳しいものとなり、結果として一定以上の賠償金ないし解決金を支払わなければならなくなる可能性も高くなります。
4.事例紹介
以下では病院・クリニックのような医療機関において行われた懲戒処分のうち、懲戒処分が有効とされた事例、無効とされた事例を紹介いたします。
(1) 懲戒処分が無効とされた事例
最初に医療機関における懲戒処分が無効とされた事例(平成元年3月23日)について紹介いたします。本事例は上司に対する反抗的態度及び嫌がらせを行っており、当該行為に対して一度懲戒処分(戒告処分)を行ったにもかかわらず上記問題行動を継続した事案です。かかる事例において、裁判例では、当該看護師に不適切な言動があり、以前懲戒を受けていた事案と同様の行為を行ったということを考慮しつつ、懲戒解雇に該当するほどの重大な非違行為は認められないとして、懲戒解雇を無効としています。
(2) 懲戒処分が有効とされた事例
続いて医療機関において行われた懲戒処分が有効とされた事例(大阪地裁平成8年3月29日)について紹介いたします。本事例は、看護師が医師が紹介した病院と異なる病院を紹介した、相当長期間にわたって勤務中に団体交渉の文字起こしをしていた看護師に対して懲戒解雇をした事案です。かかる事例において、裁判例では、そのような看護師の行為は患者に損害を及ぼしかねない重大な非違行為であり、これに対し懲戒解雇を持って臨むのはやむを得ないとして懲戒処分を有効としています。
5.千瑞穂法律事務所ができること
以上のとおり、医療機関における問題社員対応は、その段階に応じて取るべき対応は異なります。
そして、医師に専門とする科があるように、弁護士にもそれぞれが得意とする分野があり、適切な対応をするためには、それを得意とする弁護士に依頼する必要があります。
千瑞穂法律事務所は、使用者側の労働法務を中心分野としており、現在、80社を超える企業様と顧問契約を締結しております。当事務所では、使用者側の弁護士として、病院・クリニックの院長や人事担当者様が抱える悩みに寄り添い、全面的にサポートしていきます。
具体的には、スタッフによる問題行動があったかどうかの事実調査や、問題社員への対応方法の指南、問題社員への退職勧奨を行うほか、今後同様の問題が生じた際に適切な対応ができるよう就業規則に対して弁護士目線でのコメントをするということを行っております。
問題社員の対応についてお悩みの病院・クリニックの院長や人事担当者様は、お気軽にご相談ください。