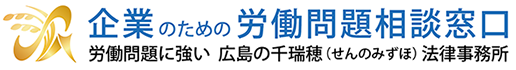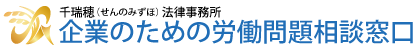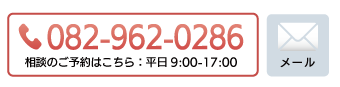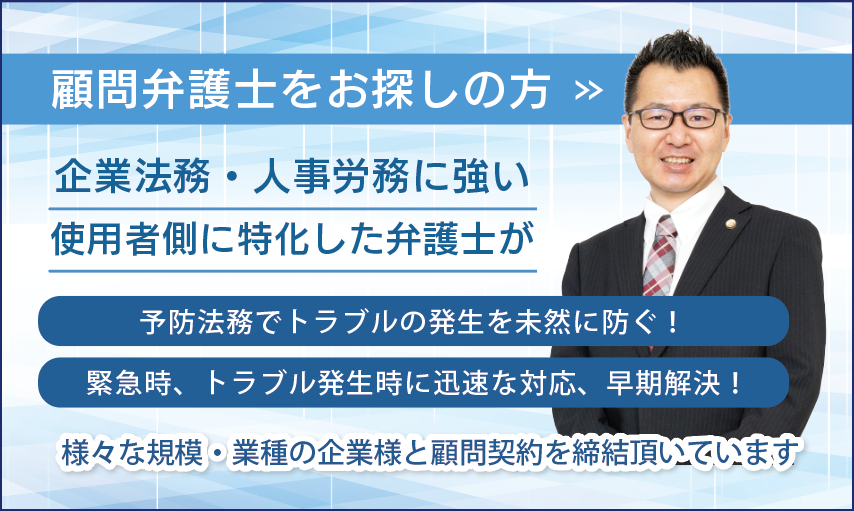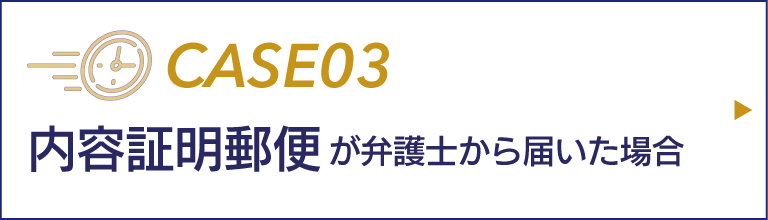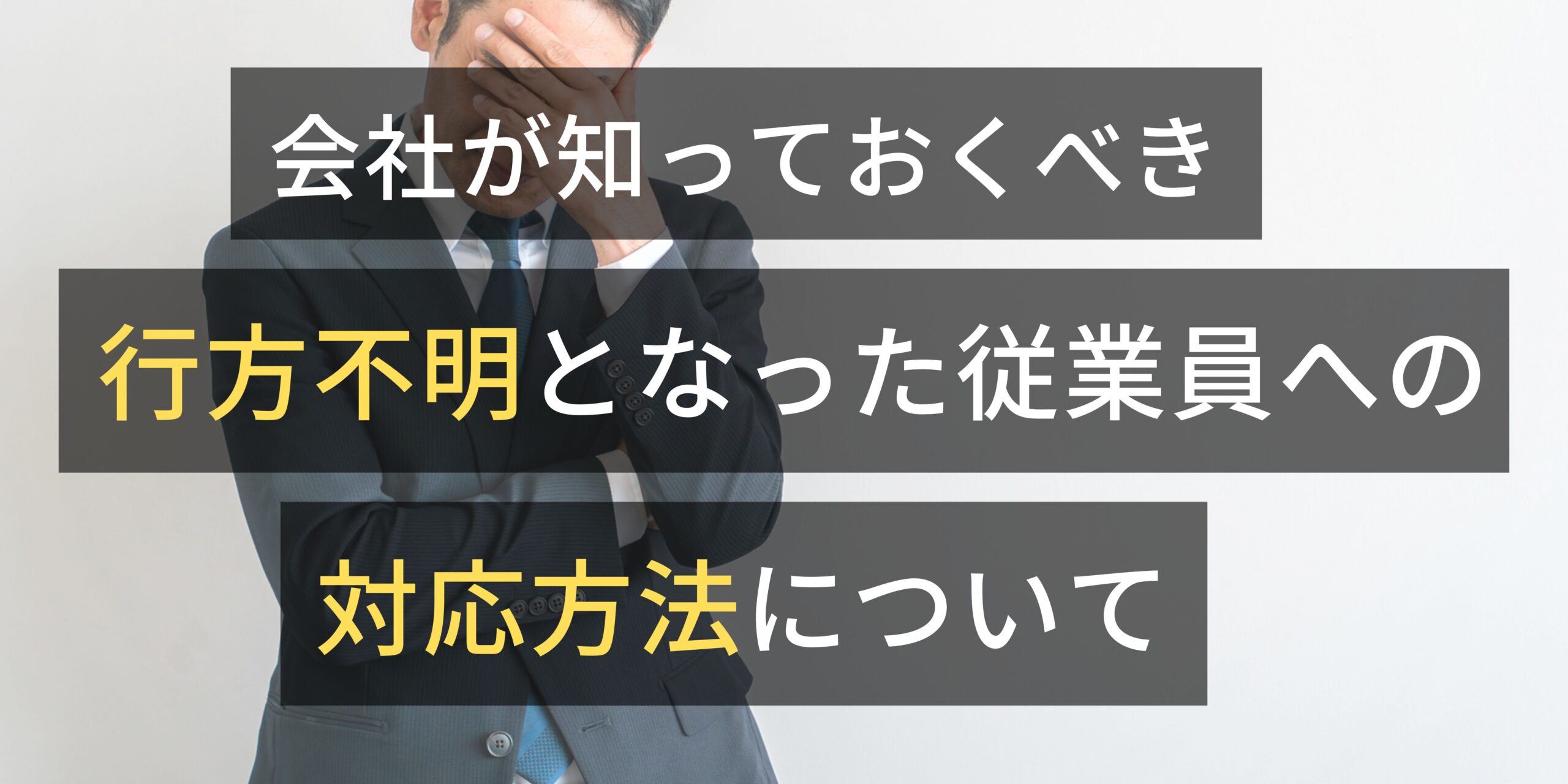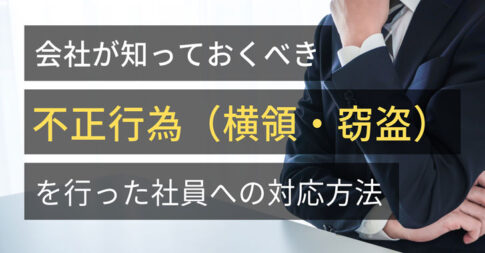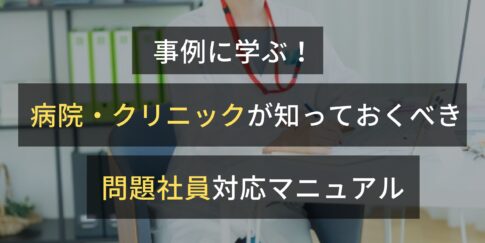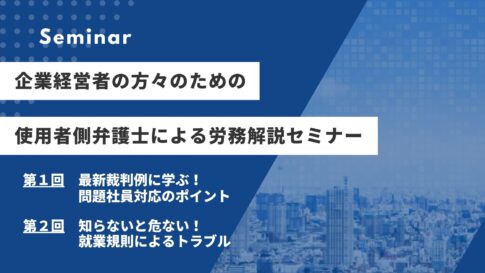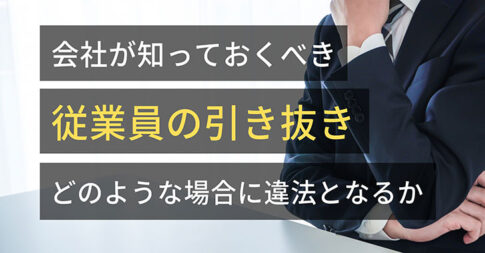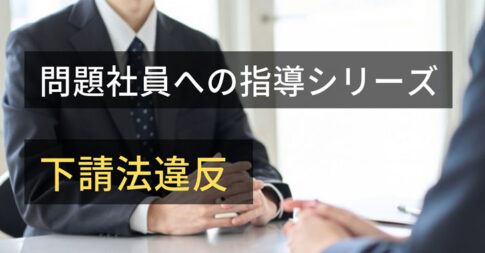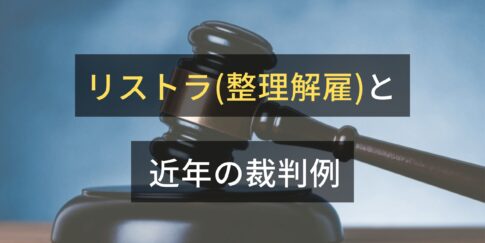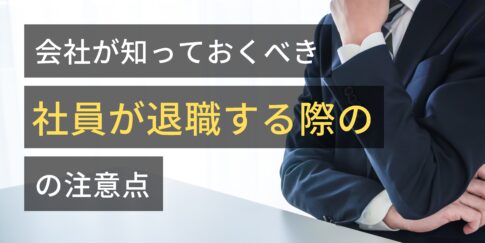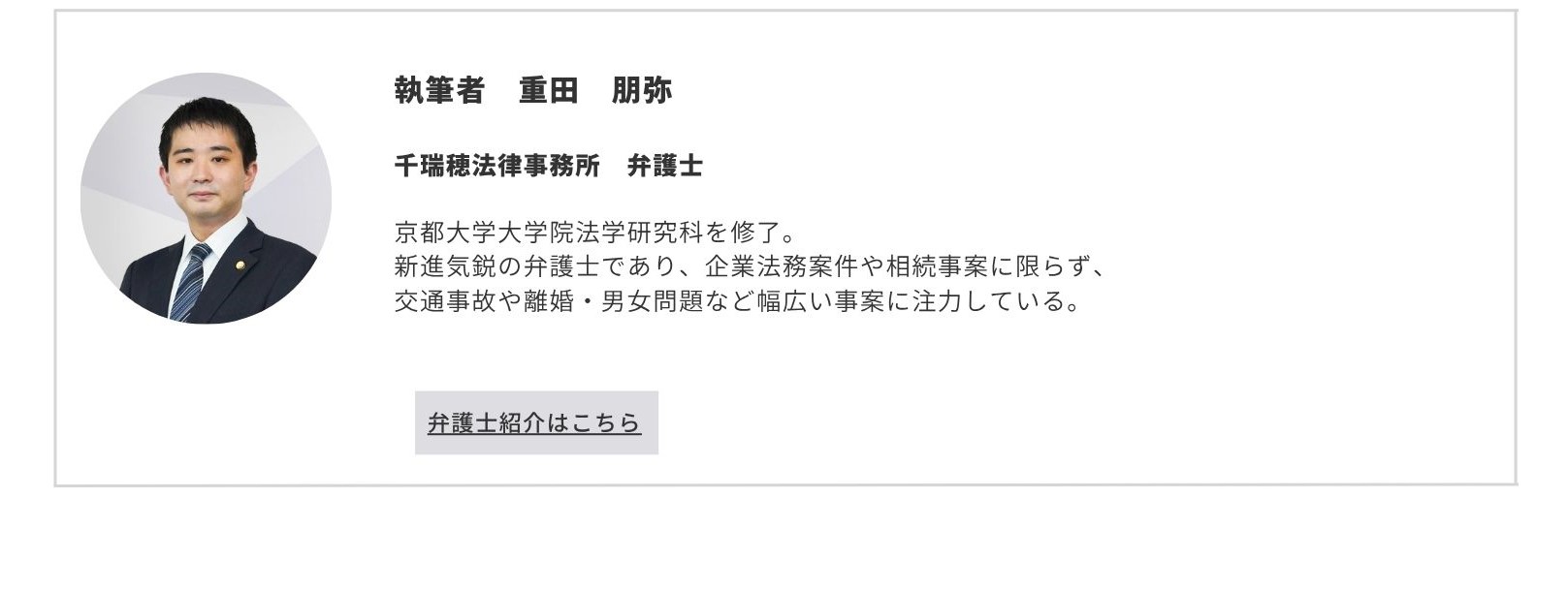
従業員が会社に来ないまま連絡も取れないという事態が生じた場合、会社としてはどのように対応するべきでしょうか。
従業員の数が一定数いるような企業様では、ある日突然従業員と連絡がつかなくなり、行方不明となるといった事態が生じることもあると思います。
従業員が会社に来ないからと言って会社側が安易に解雇手続きを進めた場合、のちに当該従業員から解雇無効を争われたり、場合によっては損害賠償請求をされたりするリスクがあります。もっとも、そのようなリスクを恐れて、当該従業員を解雇せず、放置しておくと、社会保険料、労働保険料の負担など、会社に生じる負担は決して軽いものでないことは言うまでもありません。
そこで、本記事では、従業員が行方不明になった際に会社が行うべき対応をご説明いたします。
目次
1. 行方不明の従業員を解雇するハードルについて
(1) 行方不明となった従業員を懲戒解雇とすることができるか
従業員が会社に来なくなった場合、当該従業員を放置することは、前述のとおり会社に生じる不利益は大きいものといえます。そのため、会社としては、業務命令違反として、当該従業員を懲戒解雇することを考えると思われます。
しかし、行方不明となった従業員を懲戒解雇とする場合、無断欠勤の理由によっては、当該解雇が無効であるとして争われる可能性があることを留意すべきです。
具体的には、精神的な不調で欠勤していた労働者が、有給休暇を消化した後、欠勤届を出さないまま欠勤を続けていた事案で、使用者としては、精神科医による健康診断を実施してその診断結果等に基づいて休職等の措置を検討し経過を見るなどの対応をとるべきであったとして、懲戒処分を無効とした判例があります(最二小判平24.4.27)。
懲戒解雇による解雇は一定の重大事由がなければ認められにくいことは、前述のとおりです。もっとも、長期の不就労は労務の不提供という雇用契約(民法623条)上の債務の不履行に当たるため、当該欠席が業務上の傷病によるものである場合等を除き、普通解雇を行うことができる可能性が高いです(労働契約法16条)。したがって、従業員が出勤しない状態となった理由が不明な場合には、普通解雇を行うことも検討するべきであるといえます。
(2) 解雇のハードルと対応策
上記のとおり、従業員が無断欠勤する場合、少なくとも普通解雇による限り、解雇を行うことは適法である可能性が高いと考えられます。
もっとも、解雇を行うにはその意思表示を相手に到達させる必要があるところ(民法97条)、欠勤を続けている従業員に対してどのように解雇の意思表示を到達させるかが問題となります。従業員が未成年の場合には、親権者、法定代理人である両親に対して解雇の意思表示を行うことができます(民法5条、818条)。しかし、それ以外の場合には「公示による意思表示」(民法98条1項)によることになります。もっとも、公示による意思表示は、効力が生じるまでに一定の時間がかかる(民法98条3項)というデメリットがあることにも留意するべきです。
また、従業員に対する解雇の意思表示の到達の効力が争われた裁判例として兵庫県事件(最一小判平11.7.15)があります。当該事案は、地方公務員を懲戒免職とした事案で、「辞令及び処分説明書を家族に送達すると共に、処分の内容を公報及び新聞紙上に公示」することにより、当該処分が被処分者の了知しうる状態に置かれたものとして、解雇の意思表示が被処分者に到達したものとして解雇を有効としています。かかる事案は、公示による意思表示によらず解雇の意思表示の到達を認めた判例です。もっとも、どの段階で解雇の意思表示が従業員の了知しうる状況になったといえるかについては法的評価を伴うものであるから、判断権者によって判断が分かれうることからすれば、安易に解雇の意思表示の到達が認められると考えるべきではありません。
以上から、行方不明となった従業員を解雇する場合にはどのようにその意思表示を到達させるかという点で法的判断が必要となります。したがって、どのように解雇の意思表示を到達させるべきか悩んだ場合には専門家に相談するべきであると思われます。
(3) その他の対応
解雇の意思表示を到達させることが困難である場合、公示による意思表示を行う以外のより簡易な対応として、従業員の親族や身元保証人に対して解雇の意思表示をしたり、当該従業員の代理人として退職届を提出したりしてもらう方法がありえます。
もっとも、これらの者は必ずしも従業員の代理権を有しているわけではないことから、後にそのような方法による退職又は解雇の効力を争われるリスクがあることは留意する必要があります。
2. 社員が行方不明であることが発覚した場合に会社が行うべきこと
(1) 無断欠勤の原因の調査
1(1)に記載したとおり、従業員が無断欠勤を続けている理由次第では、当該社員を懲戒解雇するかどうかや、当該社員に退職金を支払うべきかなど、使用者として当該従業員に取るべき対応は変わり得ます。
そのため、社員がいなくなった場合には、まずは、当該従業員の家族に連絡を試みたり、居所を訪ねたりするなどして、当該社員のいなくなった原因を調査することが必要となります。また、後に解雇の効力を争われた場合に備えて、調査の際に見つかったものや調査記録を証拠化しておくことも重要となります。
(2) 退職の意思表示の有無の確認
本人が退職届を提出している場合等、本人による退職の意思表示があったと認められる場合、自己都合退職として扱える可能性があることから、(1)の原因の調査のほか、本人の退職の意思表示があるかどうかも合わせて調査するべきです。仮に明示の退職の意思表示が認められない場合であっても、本人のSNS上の投稿等から本人の黙示の退職の意思表示が認められることもありうることから、当該投稿もスクリーンショット等を行うことにより証拠化しておくべきです(労務専門弁護士が教える SNS・ITをめぐる雇用管理―Q&Aとポイント・書式例 新日本法規 2016年 126頁参照)。
もっとも、退職という本人にとって重要な意思表示であり、仮に黙示の退職の意思表示が認められるかどうかが裁判で争いになった場合、黙示による意思表示があったかは厳格に判断される可能性が高いことから、安易に黙示の意思表示による退職を認定することはリスクが高いといえます。
3. 行方不明となった社員の取り扱いに対する予防法務について
以上のとおり、原因不明の無断欠勤となっている社員を解雇することには一定のハードルがあるといえます。このような事態が生じることを防ぐ予防法務として、従業員が一定期間勤務しない場合には当然に自然退職とする規定を就業規則においておくことが考えられます (労働法実務体系 第2版 民事法研究会 2019年 540頁参照)。
もっとも、上記規定を設けたとしても、従業員が出勤しなくなった理由次第では、自然退職規定による退職が無効となる場合があることも留意すべきです。具体的には、従業員が業務上の理由により傷病となった場合に自然退職としたことが労働基準法19条の趣旨に反するとして自然退職を無効とした事例があります(東京地裁平29.3.13)。
4. 千瑞穂法律事務所ができること
従業員が行方不明になった場合、後に解雇の効力を争われるといった事案が頻繁に起こるとは想像しにくいです。もっとも、行方不明となった従業員を辞めさせる場合には、以上で説明したような法的リスクが伴うことは認識しておくべきでしょう。
また、従業員の状況から退職の意思表示があったものとして扱ってよいか、懲戒解雇と普通解雇のいずれの解雇によるべきか、解雇を誰にどのように伝えれば解雇の意思表示を到達したものとして扱えるかなど、行方不明になった社員に対する対応は専門家による判断が必要な場合が多いです。
千瑞穂法律事務所では、使用者側の弁護士として全面的にサポートしていきます。
具体的には、予防法務としての就業規則チェックはもちろん、そのような就業規則ができていない場合に行方不明となった従業員に対して、いかなる手続きでどのような処分をするかというような今後の方針について、リーガルコメントを提供することを行っております。
行方不明となった社員に対する対応についてお悩みの企業様は、お気軽にご相談ください。