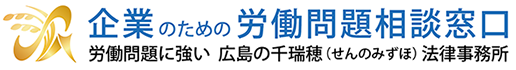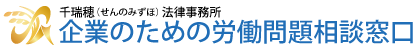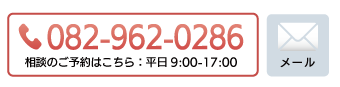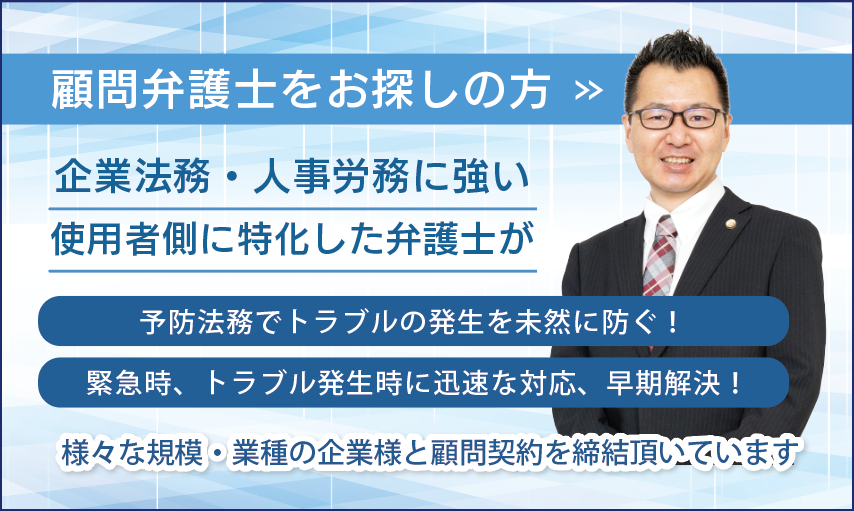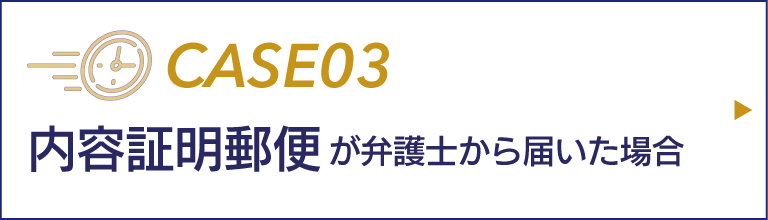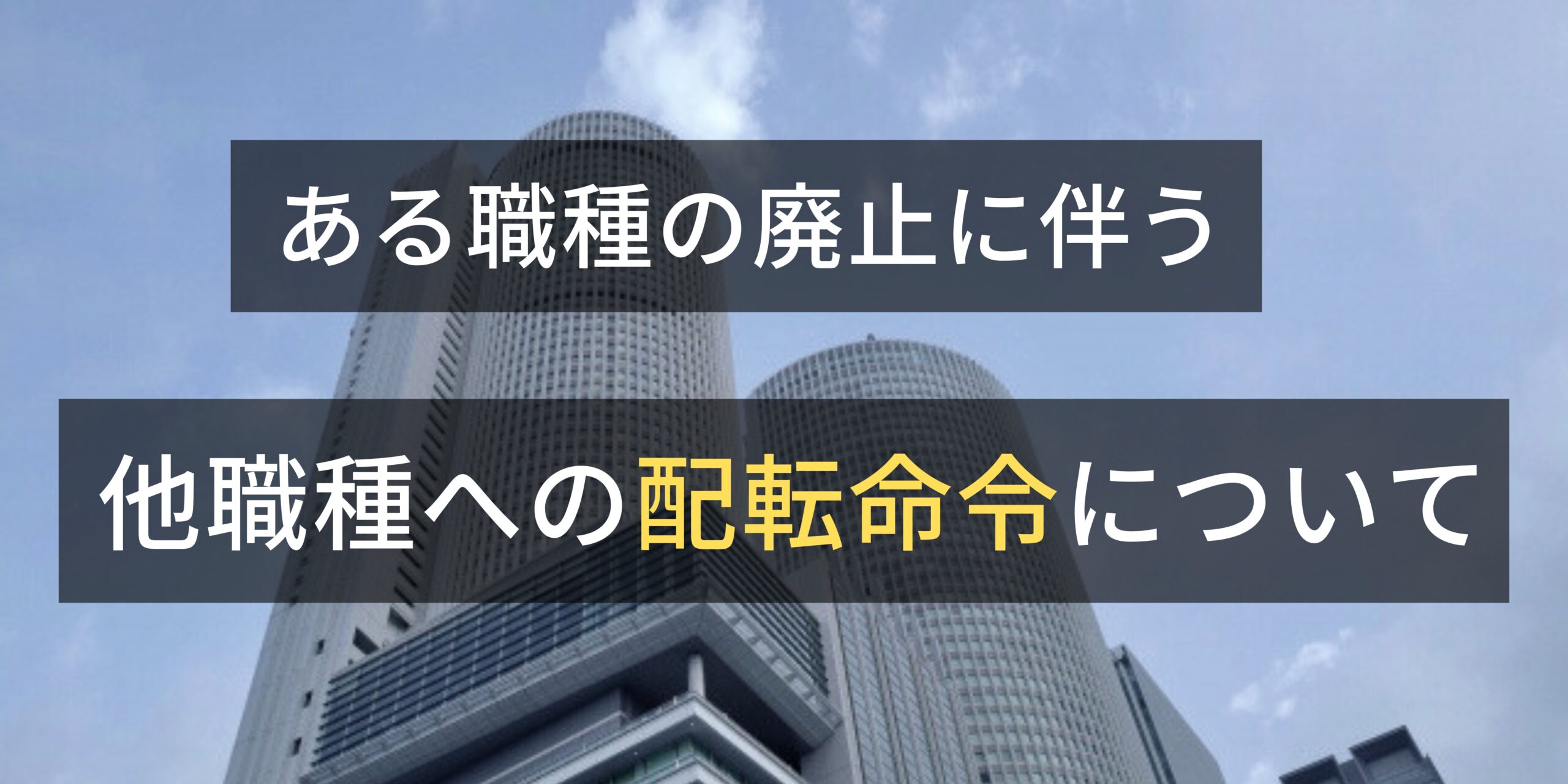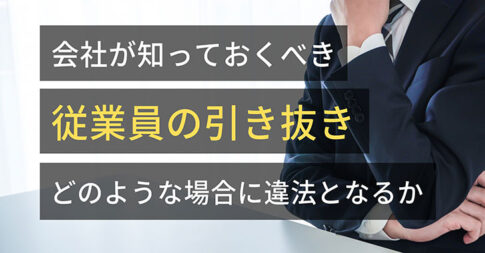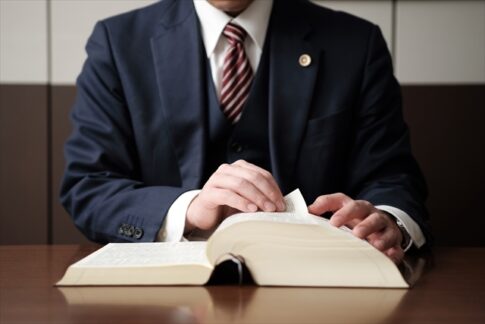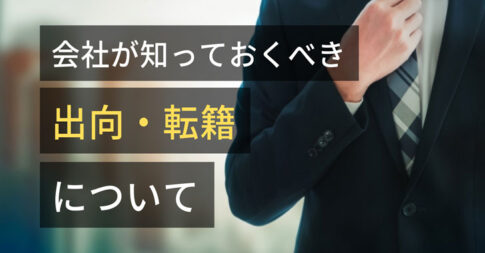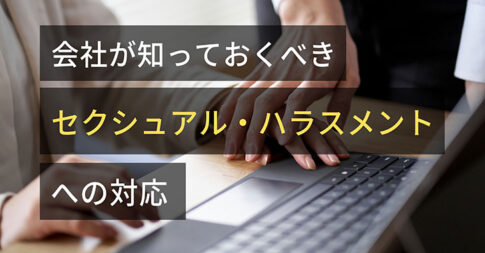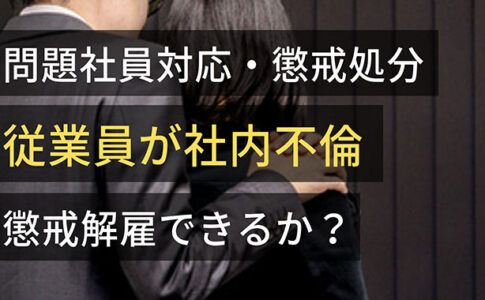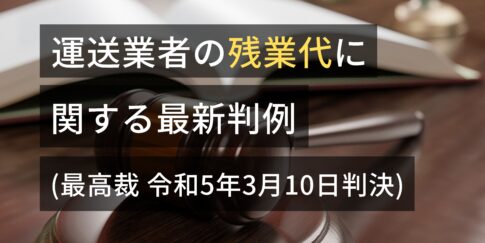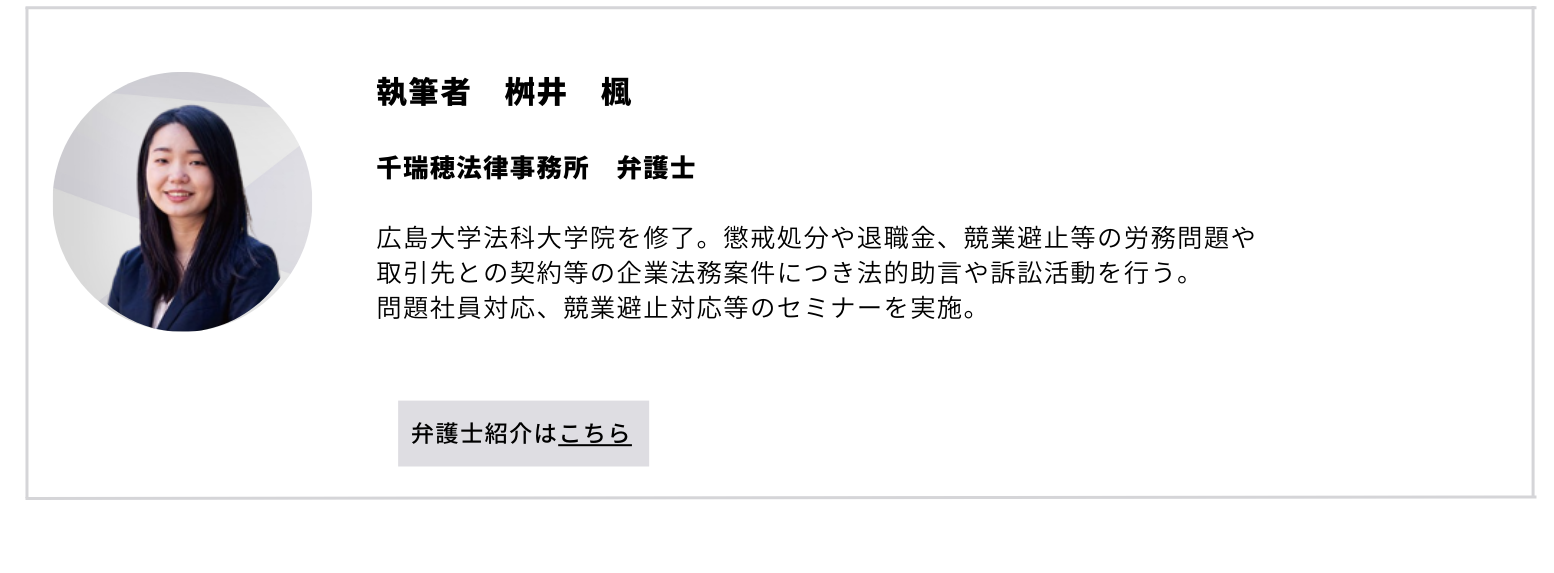
配転が問題になった事案について、令和6年4月26日に最高裁で判断がなされました(最二小判令和6年4月26日判決)。
具体的には、福祉用具の改造・製作を担当とする技術職として就労していた従業員について、福祉用具の開発・製作業務の廃止により別の職種(総務課・施設管理担当)へ配転命令をしたことが、職種限定合意に反するとされたものです。
この判決の考え方は、今後企業での配転の対応にあたって参考になると考えられますので、以下この判決についてご説明いたします。
1 事案
・Xは、平成13年3月、Y法人に、福祉用具センターにおける福祉用具の改造及び製作並びに技術の開発(以下、併せて「本件業務」という。)に係る技術職として雇用されて以降、上記技術職として勤務していた。
・XとY法人との間には、Xの職種及び業務内容を上記技術職に限定する旨の合意がある。
・Y法人では、福祉用具センターにおける福祉用具改造・製作業務を廃止する方針を決定した。
・Y法人は、Xに対し、その同意を得ることなく、平成31年4月1日付けでの総務課施設管理担当への配置転換を命じた(「本件配転命令」)。
・XがY法人に対して、損害賠償請求を求め訴訟提起。
・高等裁判所は、本件配転命令は配置転換命令権の濫用に当たらず、違法であるとはいえないと判断し、本件損害賠償請求を棄却すべきものとした。
・Xが上告。
配転とは、労働者の配置の変更であって、職務内容または職務場所が相当の長期間にわたって変更されるものを指します。
配転については、就業規則で根拠規定が定められていることが多いですが、このような根拠規定がある場合であっても、従業員と職種を限定する合意をしたり、勤務場所を限定する合意をした場合、これらの従業員との合意が優先されると考えられています。
そのため、本件のように職種を限定する合意がある場合、会社は従業員の同意なく合意した職種以外の職種へ配転命令をすることはできない(①会社に他の職種への配転命令権がない)と考えられます。なお、配転命令権があると判断された場合には、②配転命令が権利濫用とならないかが問題となります。
本件は、Xが行っていた職種自体が廃止されることになったという事情があり、会社はXを解雇しないようにするため、ある意味Xに配慮して配転命令をしたとも考えられます。本件は、このような場合にも配転命令が違法となってしまうのかが問題となりました。
そして、原審(大阪高裁令和4年11月24日判決)では、XとY法人との間で職種限定合意があることを前提としつつも、「解雇もあり得る状況のもと、これを回避するためにされたものであるといえるし、・・・本件配転命令に不当目的があるとは言い難い」、「本件配転命令が違法無効であるとはいえない。」と判断していました。
2 判断内容
最高裁は、本事案の配転命令に関して以下のとおり判断しました(以下の「(X)」、「(Y法人)」は筆者が追記したものです)。
労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。
上記事実関係等によれば、上告人(X)と被上告人(Y法人)との間には、上告人(X)の職種及び業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人(Y法人)は、上告人(X)に対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったものというほかない。
そうすると、被上告人(Y法人)が上告人(X)に対してその同意を得ることなくした本件配転命令につき、被上告人(Y法人)が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
最高裁は、本件のように業務が廃止されるに伴い、解雇を回避するために配転命令を行ったというような事情があっても、個別的な同意がない限り、職種限定合意に反する配転命令はできないといった立場を示しました。
そして,本件配転命令について不法行為を構成すると認めるに足りる事情の有無や,被上告人(Y法人)が上告人(X)の配置転換に関し上告人(X)に対して負う雇用契約上の債務の内容及びその不履行の有無等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
最高裁は、配転が違法であるとして、それが不法行為に該当するか否か等を判断させるために原審へ差し戻すこととしました。
そして、差戻審(大阪高裁令和7年1月23日判決)では、以下のように判断し、従業員の損害賠償請求を認めました。
【差戻審(大阪高裁令和7年1月23日判決)の判断内容】
被控訴人(Y法人)は、控訴人(X)を本件業務に係る技術職以外の職種に就かせることを想定していなかった上、控訴人(X)においても、本件配転命令の発令前に、被控訴人(Y法人)に対し、本件面談を通じて、本件業務に係る技術職を続けたい旨を訴えていたのであるし、L課長が控訴人の前で改造・製作業務をやめるという趣旨の発言をしたときも、被控訴人(Y法人)の内部相談窓口に対し、控訴人(X)の業務を否定することであり、パワーハラスメントに該当するとの通報をしているなど、本件合意の存在をうかがわせる対応をしており、被控訴人(Y法人)としては、本件合意の存在を容易に認識できたというべきであるから、被控訴人(Y法人)には本件配転命令を行ったことについて過失が認められる。
したがって、被控訴人(Y法人)による本件配転命令は、控訴人(X)に対する関係で、不法行為を構成するというべきである。
差戻審では、本事案の具体的な事情を踏まえて、不法行為に該当するか否かを判断しているため、事案によっては、過失が認められない等の判断もあり得るのではないかと思います。
3 まとめ
上記の判決の内容を踏まえると、ある業務を廃止する等の事情が発生した際に企業側がよかれと思って従業員の配転をしようと考えても、従業員との間に職種限定合意がある場合は、当該従業員の同意を得ない限り配転は困難と考えられます。
企業としては、このような場合、まずは従業員に配転をするか否か、又は退職を希望されるのか等の選択肢を打診し、従業員の意向を確認しながらできる限り話し合いをすることが必要になると思います(話し合いをしたことや内容を録音等で証拠として残しておくことも必要です)。
そして、従業員が配転に応じず、従業員を解雇せざるをない場合、整理解雇の要件(人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履践、被解雇者の選定の妥当性、手続の妥当性)を備えているかがメルクマールとなると考えられます。
4 千瑞穂法律事務所にできること
千瑞穂法律事務所では、使用者側の人事労務(労働)問題を多数扱っており、本件のような配転に関しても多くの企業様にアドバイスをさせていただいております。
業務を廃止する等により、従業員の配転を検討することはしばしばあると思いますが、配転の根拠があるか、職種限定合意があると考えられるのか、従業員との話し合いをどのように行うか、どの程度話し合いをする必要があるか、適法に解雇できるのか等悩まれる場合もあると思います。これらの点は事実関係や会社の規模等によって異なりますので、判断に悩まれる場合は、千瑞穂法律事務所にお気軽にご相談ください。