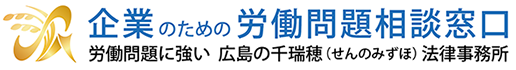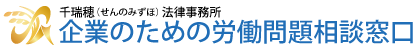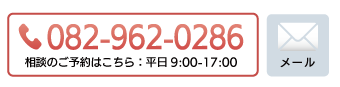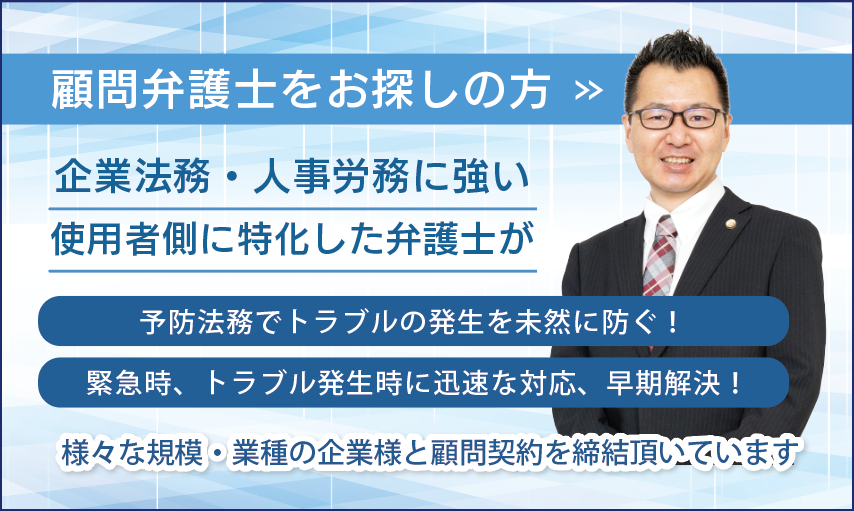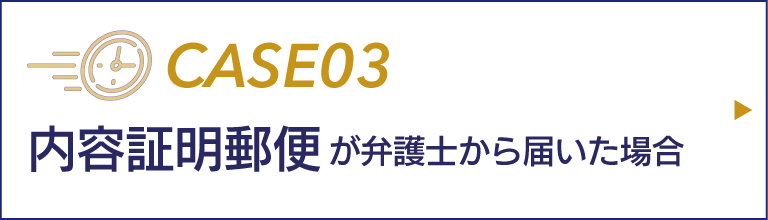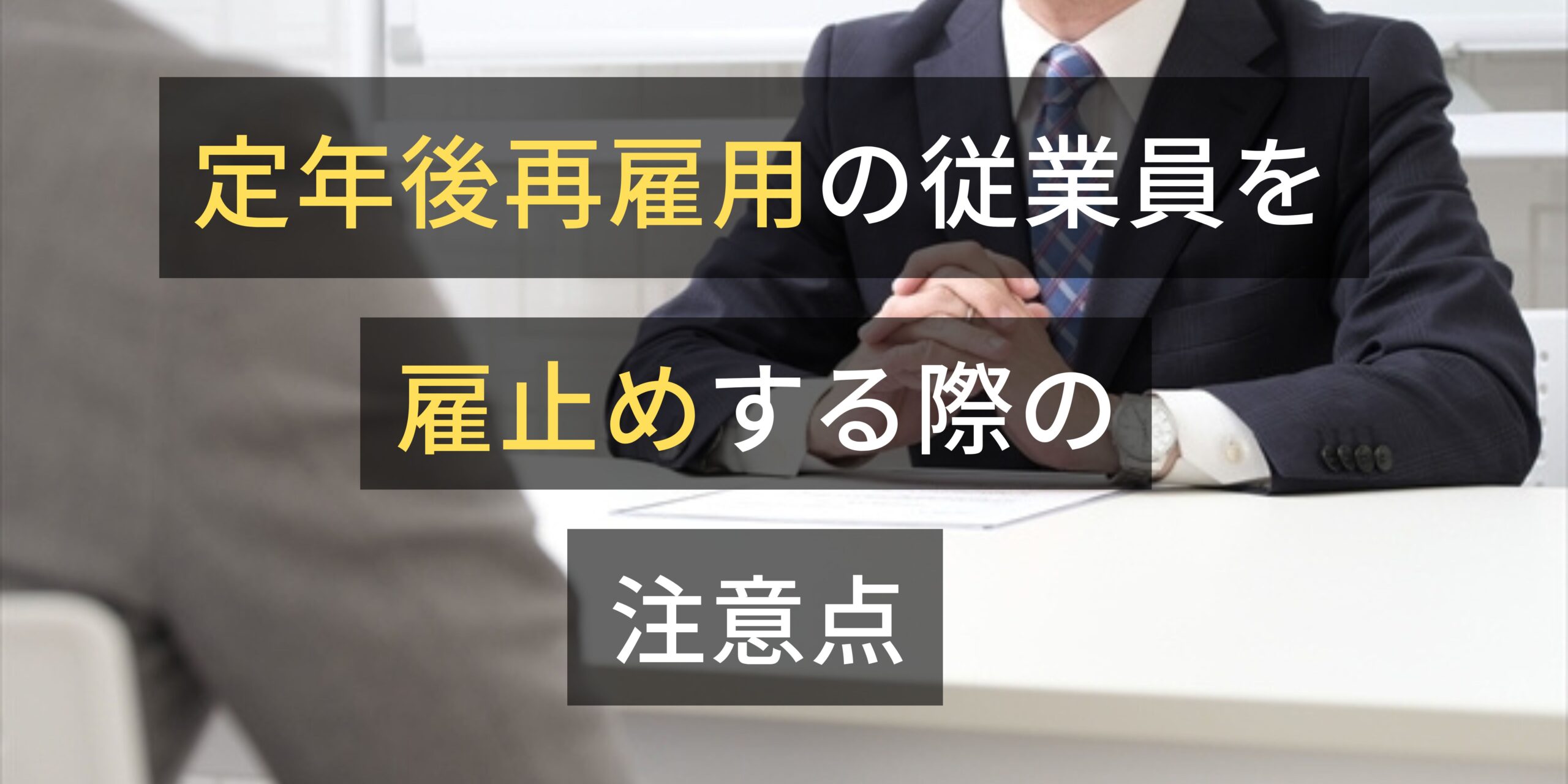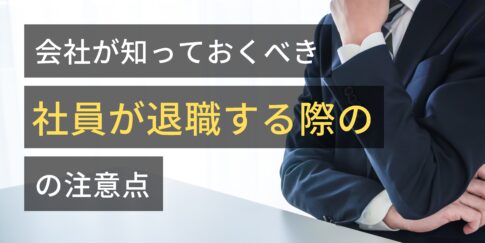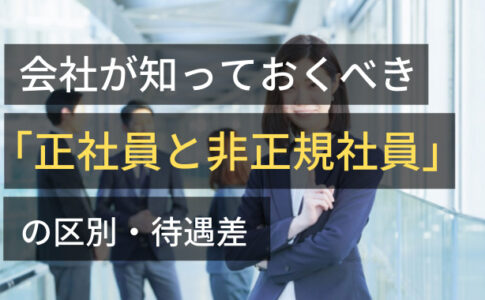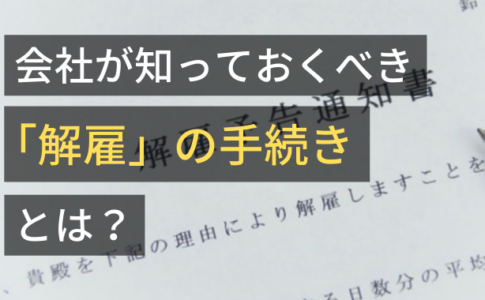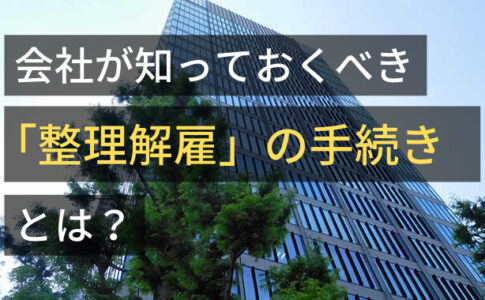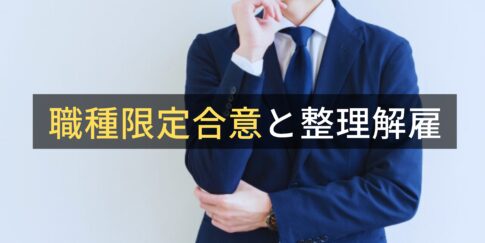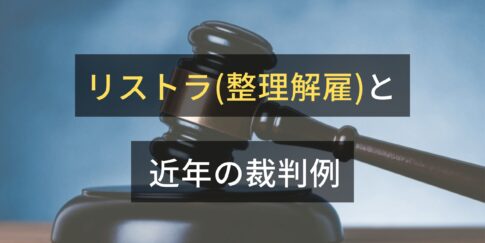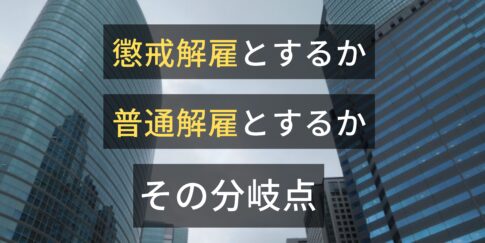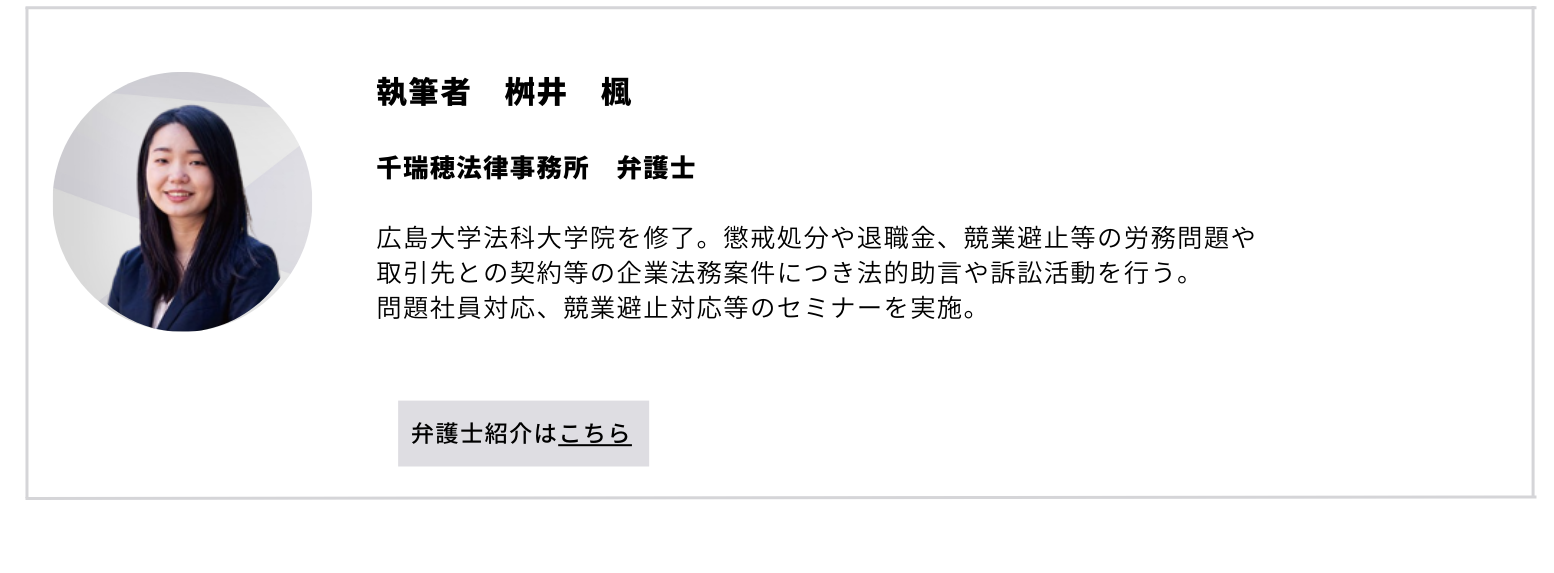
現在、高年齢者雇用安定法により、定年(65歳未満)の定めをしている事業主に対し、65歳までの安定した雇用を確保するための高齢者雇用確保措置を講じることが義務付けられており、65歳や70歳を超えても働き続けている方も増加しています。
他方で、年齢等の事情により、定年後再雇用の従業員に体調不良が生じたり、パフォーマンスが低下するといった問題が発生することがあり、雇用を継続するか否か悩まれることもあると思います。
そこで、本記事では、定年後再雇用の従業員を雇止めする場合の注意点について、ご説明いたします。
目次
1 高年齢者雇用安定法による雇用確保措置について
高年齢者雇用安定法では、65歳未満の定年制を導入している事業者に対して、①65歳までの定年引き上げ、②定年制の廃止、③65歳までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を講じることを義務付けています。
また、改正(令和3年4月1日施行)により、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主に対し、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、70歳までの定年引き上げ、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度の導入、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入等の措置を講ずる努力義務も課されています。
上記の雇用確保措置のうち、現在は65歳までの継続雇用制度(定年後再雇用)を導入しておられる会社が多数と思われます。
2 定年後再雇用の従業員の雇止め
上記1の65歳までの継続雇用制度として、従業員の定年後1年間の有期雇用契約を締結し、これを毎年更新するという対応をしておられる会社が多いと思います。
この場合、従業員の方の状況等によって、従業員を雇止め(期間満了とともに辞めてもらうこと)することを検討されることもあると思います。雇止めする場合、期間満了なのだから雇止めは当然有効になるのではないかと考えてしまいますが、必ずしもそのようになるわけではないので、慎重に考える必要があります。
以下、雇止めに関して詳細に説明いたします。
(1)雇止めに関する法律上の定め、考え方
労働契約法19条は有期労働契約の更新等について定めており、簡略すれば、
・過去に反復して更新されたことがあるものであって、期間の定めのない労働契約と同視できる場合(1号)
・従業員において契約期間の更新がなされるものと期待することについて合理的な理由がある場合(2号)
には、雇止めが有効になるために「客観的に合理的な理由と社会的相当性」が必要となります。
定年後再雇用の場合、上記1のとおり、事業者に高年齢者雇用安定法による65歳までの雇用確保措置が義務付けられていることから、例えば60歳で定年後再雇用となった従業員を、会社が期間満了で雇止めしたいと考えたとしても、「従業員において契約期間の更新がなされるであろうと期待することについて合理的な理由がある場合」(労働契約法19条2号)に該当する可能性が高いと考えられるため、雇止めをするためには「客観的に合理的な理由と社会的相当性」が必要となります。
「客観的に合理的な理由と社会的相当性」の判断の厳格さは、更新への期待の内容や程度によって異なると考えられます。
定年後再雇用の方の問題行動や能力不足等が契機となって雇止めを検討することもしばしばありますが、「客観的に合理的な理由と社会的相当性」があると認められるためには、少なくともいつどこでどのようなこと(問題行動)があったのかが分かる資料、それに対して会社側が行った対応(面談での注意指導等)について証拠を残しておく必要があります。
(2)契約更新の上限を設けることについて
多くの企業において、就業規則等で定年後再雇用の場合の更新の上限を65歳と定めています。事案にもよりますが、現状65歳を更新の上限とすることは有効と判断される可能性が高いと考えられます。なお、65歳未満を上限とした場合には、上述した高年齢者雇用安定法が65歳までの雇用確保措置を講ずる義務を設けていることから、同法に抵触する可能性があります。
判例(最判平成30年9月14日判決)では、「被上告人の事業規模等に照らしても、加齢による影響の有無や程度を労働者ごとに検討して有期労働契約の更新の可否を個別に判断するのではなく、一定の年齢に達した場合には契約を更新しない旨をあらかじめ就業規則に定めておくことには相応の合理性がある」とされています。
(3)更新の上限を超えて雇用を継続する場合の注意点
定年後再雇用の従業員のうち、特定の従業員だけは更新の上限で雇止めとせずに引き続き勤務してもらいたいといったこともあると思います。
特にタクシー業界などでは65歳以上の従業員が多く、70歳を超えても働いている方も多く見かけます。
例えば60歳から定年後再雇用となり、有期雇用契約を更新し続け、通算5年以上働いた場合、無期転換申込権が発生します(例外として、無期転換申込権が発生しないこととする特例もあります)。
そして、無期転換申込権を行使された場合、第二定年などのルールがなければ、解雇や本人による退職の申し出、死亡等の事情がない限り、その従業員が働き続けることができる状況になりかねません。また、従業員を解雇することは容易ではありません。
年齢を重ねる毎に体力等の衰えによる問題や認知症が疑われるような状況も生じうること、解雇にはリスクもあることから、就業規則に第二定年の規定を設けること等を検討いただくべきと考えます。
また、更新の上限を超えて雇用を継続されている従業員がいると、別の従業員が更新の上限で雇止めされた際に「あの人は更新の上限を超えても働いているのだから、私も同様に更新されるであろう」といった更新に関する期待が生じてしまうことから、労働契約法19条各号に該当する可能性があるため、従業員を更新の上限がきたという事実だけで雇止めすることが困難となると思われます。
(4)参考裁判例(東京地裁令和2年5月22日判決)
雇止めに関して参考になる裁判例を一つご紹介いたします。
67歳が定年となっている会社(タクシー事業を営む)において、定年を迎えた従業員(運転手)と定年後に嘱託契約を締結したケースで、会社が行った雇止めが無効になったものです。
ア 事案
・被告はタクシー事業を営む会社であり、原告はタクシー運転手として勤務していた。
・原告と被告は、昭和57年に期間の定めのない雇用契約を締結し、原告は平成29年、
67歳で定年退職した。
・原告は、定年退職後、被告との間で、1年間の嘱託雇用契約を締結。
・平成30年、原告と被告の間の嘱託雇用契約は更新される。
・平成30年11月、原告は接触事故を起こし、警察や営業所に連絡することなく引き続
き営業を続けた。
・被告は、平成31年で雇止めを行った。
・原告が、地位確認等を求めて訴訟提起。
・被告の会社では、運転手全体のうち70歳以上の運転手が16%を占めている。
イ 判断内容1(労働契約法19条各号該当性)
本件は、上記2(1)でご説明した雇止めが労働契約法19条に抵触しないかが問題となりました。
そして、裁判所は、本件が労働契約法19条各号に該当するか否かについて、
「本件についてみると,前記前提事実及び認定事実によれば,被告においては,タクシー運転手が定年である67歳に達した後も,嘱託雇用契約を締結して雇用を継続してきたこと,被告のタクシー運転手のうち,70歳以上の運転手は16パーセントに上ること,原告は,昭和57年に入社後からタクシー運転手として勤務し,定年退職後の嘱託雇用契約についても契約書や同意書等の書面の作成がないまま,嘱託雇用契約を一度更新したことが認められ,これらの事実に照らすと,69歳に達した原告においても,体調や運転技術に問題が生じない限り,嘱託雇用契約が更新され,定年前と同様の勤務を行うタクシー運転手としての雇用が継続すると期待することについて,合理的な理由が認められるというべきである。」
として、少なくとも労働契約法19条2号に該当すると判断されました。
被告側からは、「被告における嘱託雇用契約者の年齢及び原告の年齢が,高年法の定める雇用確保措置の上限年齢を超えていることや,タクシー事業においては,不適格者を乗務から外す必要性が高いこと,原告と被告との間の嘱託雇用契約の更新回数が1回であることなどから,原告が嘱託雇用契約を更新されるものと期待することに合理的理由はない」といった指摘がありましたが、裁判所は「被告の指摘する点は,いずれも直ちに雇用契約が更新されるとの期待を持つ合理的理由を否定するものとはいえず,被告における嘱託雇用契約の実態や,他の労働者の嘱託雇用契約の更新状況を踏まえると,前記判断を左右するものではない。」と判断しました。
この内容から、高年齢者雇用安定法の雇用確保措置の上限年齢(65歳)を超えて雇用されているからといって更新の合理的期待が直ちに否定されるわけではなく、契約の実態や他の労働者の更新状況が重視されると考えられます。
ウ 判断内容2(「客観的に合理的な理由と社会的相当性」の存否)
裁判所は、「本件接触は,左後方の不確認という比較的単純なミスによるもので,接触した自転車の運転者は,ドライブレコーダーの記録から受け取れる限り,倒れた様子は見受けられず,接触後すぐに立ち去っていることから,本件接触及び本件不申告は,悪質性の高いものとまではいえない。後に事案を把握した警察においても,本件接触や本件不申告を道交法違反と扱って点数加算していないことも踏まえれば,本件接触及び本件不申告は,警察からも重大なものとは把握されていないことがうかがわれる。」として、その他、原告が自ら接触を報告、注意指導に対する反省、車両に修理が施された証拠がないこと、原告が三十数年間人身事故を起こすことなく、表彰されるなど優秀な運転手であったこと、事故の相手方が無言で立ち去ってしまっていたこと等を踏まえ、接触事故と会社への不申告のみを理由に雇止めすることは重すぎる(客観的に合理的な理由と社会的相当性は認められない=雇止め無効)としました。
3 千瑞穂法律事務所ができること
千瑞穂法律事務所では、使用者側の人事労務(労働)問題を多数扱っており、定年後再雇用の従業員の雇止めに関する経験も豊富です。
例えば、定年後再雇用の従業員を更新上限(65歳)で雇止めを行い、従業員側から65歳を超えても更新される期待があるとして訴訟提起された事案で、会社側の代理人として訴訟活動を行い勝訴した実績や裁判に至る前に円満に解決したケースも複数あります。
有効に雇止めを行うことや、従業員に円満に退職してもらうためには、事前の準備が肝要となりますので、雇止め等で悩まれることがありましたら、千瑞穂法律事務所にお気軽にご相談ください。